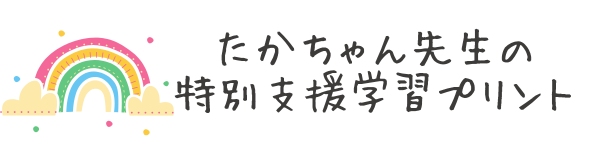発達障害や自閉症スペクトラム症の子と過ごす毎日の中で
こんな風に感じること、ありませんか?
注意しても伝わらなかったり、同じことでつまずいたり…。
本当は叱りたくないのに、つい強く言ってしまって自己嫌悪。
そんな経験をしているのは、あなただけではありません。
実は、言葉で伝えるよりもストーリーで伝えたほうが、ぐっと心に届く子どもたちがいます。
それを助けてくれるのが「ソーシャルストーリー」です。
この記事では、専門的な知識がなくても使えるように、ソーシャルストーリーの意味・効果・作り方を、実例とともにわかりやすく紹介します。
ソーシャルストーリーとは?意味と目的をわかりやすく解説
「ソーシャルストーリー」とは、発達障害や自閉スペクトラム症(ASD)の子どもが、社会のルールや人との関わり方を、わかりやすく学ぶための支援方法です。
物語の形で「どんな状況で」「どう行動すればいいか」を伝えることで、子どもが安心して社会生活を送れるようになります。
ソーシャルストーリー:キャロル・グレイの定義
ソーシャルストーリーは、1991年に教育者のキャロル・グレイが考案しました。
キャロル・グレイ氏による定義では、ソーシャルストーリーとは
「社会的な状況や出来事を、子どもが理解しやすい言葉と構成で示す短い文章」
と、されています。
つまり、ただの絵本ではなく、子どもの立場に寄り添って「どうすればよいか」を具体的に伝える支援ツールです。
例えば、
そんな場面を、短いストーリーで説明します。
この方法は教育・心理学の分野でも研究が進んでおり、自閉スペクトラム症の社会的理解を助ける有効な支援法として評価されています。
ソーシャルストーリーはどんな子におすすめ?
ソーシャルストーリーは、以下にあてはまる子に特に効果があります。
- 自閉スペクトラム症(ASD)の特性がある子
- 状況の変化に不安を感じやすい子
- 社会的なルールを理解するのが苦手な子
- 言葉での説明だけではピンとこない子
上記の子たちは、「相手の気持ち」や「暗黙のルール」をつかむことが難しい場合があります。
ソーシャルストーリーでは、視覚的(絵・写真)+言語的(文章)に情報を伝えることで、理解のしやすさがぐっと上がります。
また、発達障害だけでなく、グレーゾーンやHSC(繊細な子)にも効果的です。
どんな子でも「見通しを持てること」で、安心して行動できるようになります
ソーシャルストーリーはなぜ効果があるの?
ソーシャルストーリーが効果的なのは、「これから何が起こるのか」を子どもが理解できるからです。
つまり「見通しがもてる」から。
発達障害のある子は、見通しがもてず、予測できない状況に強い不安を感じることがあります。
そこで、あらかじめストーリー形式で見通しをもたせてあげることで、
「次は○○するんだな」
「こうしたら安心なんだ」
と心の準備ができ、落ち着いて行動できるようになります。
また、ソーシャルストーリーは「否定」ではなく「肯定」の言葉を使うため、子どもが自信をもって挑戦できるようになります。
安心感が育つことで、他の行動や学びにも良い影響を与えてくれます。
ソーシャルストーリーの効果とメリット
ソーシャルストーリーは、子どもの困りごとをやさしく理解に変える支援方法です。
以下の3つのメリットがあります。
- 社会的なルールやマナーが身につく
- 不安やパニックを減らし、安心して行動できるようになる
- 「叱る」ではなく「理解を助ける」支援になる
それぞれ見ていきましょう。
メリット① 社会的なルールやマナーが身につく
ソーシャルストーリーのメリット1つ目は、社会的なルールやマナーが身につくことです。
ソーシャルストーリーは、「順番を待つ」「話を聞く」「ありがとうを言う」など、日常のルールを伝えることで、自然に社会的なルールやマナーが身に付きます。
文章で「なぜそれが大切か」「そうするとどうなるか」を理解できるので、納得して行動に移しやすくなります。
たとえば、「順番を待つ」ストーリーでは、
「みんなが待っているときは、○○さん(くん)も待つよ。そうすると、みんなが気持ちいいね」
というように、行動の意味と結果をセットで伝えます。
こうすることで、学校や家庭でのトラブルを減らし、社会性が身につくことをサポートします。
メリット② 不安やパニックを減らし、安心して行動できるようになる
ソーシャルストーリーのメリット2つ目は、不安やパニックを減らし、安心して行動できるようになることです。
発達障害や自閉症の子の中には、新しい場所や予定変更に強い不安を感じる子がいますよね。
そんなときソーシャルストーリーを使えば「どんなことが起きるのか」を事前に物語で伝えることで、見通しが持たせてあげることができます。
例えば、
「遠足の日の流れ」や「病院に行くときの流れ」をストーリーにして読んでおくと、
「次に何が起こるか」がわかり、安心して行動できるようになります。
これを予測可能性の支援と呼び、ASDの子どもに特に効果があるとされています。
メリット③ 「叱る」ではなく「理解を助ける」支援になる
ソーシャルストーリーのメリット3つ目は、「叱る」ではなく「理解を助ける」支援になることです。
「どうしてできないの?」と叱っても、子どもが本質的に理解していなければ行動は変わりません。
そこでソーシャルストーリーは、叱る代わりに「理解を助ける方法」で支援をします。
ポイントは、否定ではなく肯定的な言葉をかけること。
✖ 「立ち歩いてはいけません」⇒ ○「イスに座って聞けるとかっこいいね」
✖「手を出さないで」⇒ ○「言葉で伝えられるといいね」
✖「騒いではいけません」⇒ ○「小さな声で話すと聞きやすいね」
このように前向きに伝えることで、
子どもが「やってみよう」と思える気持ちを育てます。
これは、行動療法や発達支援の現場でも基本的な考え方であり、
子どもの主体性と安心感を両立できる支援法として、よく知られています。
ソーシャルストーリーの作り方|簡単5つのポイント
ソーシャルストーリーのメリットは分かったけど、
「じゃあ、どうやって作ったらいいの?」と思いますよね。
次に、ソーシャルストーリーが簡単に作れる方法を5つのポイントで解説します。
- 目的を明確にする
- 子どもの視点でやさしい言葉を選ぶ
- イラストや写真で具体的に伝える
- 肯定的な言葉で安心感をもたせる
- 読み返しながら、一緒に練習する
①目的を明確にする(どんな場面で使いたいか)
まずは「どんな行動を理解してほしいか」をはっきりさせましょう。
たとえば「朝の支度をスムーズにしたい」「お友達に順番をゆずってほしい」などがありますよね。
そうした子どもたちにとっての具体的な場面を決めます。
目的が明確になることで、ストーリーが現実的で効果的になります。
②子どもの視点でやさしい言葉を選ぶ
2つ目のポイントは、子どもの視点でやさしい言葉を選ぶことです。
難しい言葉や抽象的な表現は避け、子どもの年齢や理解力に合わせた言葉で書きます。
たとえば、
△「ルールを守りましょう」⇒ ○「みんなが楽しく遊ぶために、順番をまとうね」
と伝える方がイメージしやすいですよね。
子どもの心に届くような、具体的でわかりやすい言葉を選びましょう。
③イラストや写真で具体的に伝える
3つ目のポイントは、イラストや写真で具体的に伝えることです。
文字だけでなく、実際の写真やイラストを使うと理解度がぐっと高まります。
登校の流れや「順番を待つ」姿勢を絵で見せると、視覚的にイメージしやすくなります。
特に自閉スペクトラム症(ASD)の子どもには、視覚的なサポートがとても有効です。
④肯定的な言葉で安心感をもたせる
4つ目のポイントは、肯定的な言葉で安心感をもたせることです。
「〜してはいけません」ではなく、「〜するといいね」という前向きな言葉で書きましょう。
✖ 「謝らなくちゃだめでしょう」⇒ ○「お友達にぶつかったら、『ごめんね』って言えるとすてきだね」
と伝えることで、叱られた気持ちにならず、行動の意味を理解しやすくなります。
⑤繰り返し読むこと
5つ目のポイントは、作って終わりではなく、繰り返し読むことが大切です。
親子で一緒に読む時間をもち、「今日はどうだった?」と振り返ることで、少しずつ行動に変化が見られます。子どもが安心して学べる環境づくりにもつながります。
ソーシャルストーリーの実例・テンプレート集
ここでは、家庭や学校でよくあるシーンをもとに、実際に使えるストーリー例を紹介します。
どれも短く、シンプルな言葉で書かれているので、ソーシャルストーリーを用いるときの参考にしてみてください。
朝の起きたあと、身支度のストーリー例
朝は、準備がうまくいかずバタバタしがちな時間ですよね。
「急いで」「早く!」と声をかけるより、見通しをもたせたストーリーで安心して行動できるようにするのがGood。
【例.朝の支度のソーシャルストーリー】
朝になったら、ベッドから起きます。
カーテンを開けます。
顔を洗います。
パジャマから洋服に着替えます。
朝ごはんを食べます。ぜんぶできたらお母さんがほめてくれます。
💡ポイント
- 1つずつ順番に書くことで、「何をすればいいか」が明確に。
- イラストや写真を添えると、視覚的にも理解しやすくなります。
順番を待つ・ルールを守る場面のストーリー例
順番を待つのが苦手な子どもは多いものです。
でも、「なんで待たないといけないのか」が分かれば、少しずつ我慢する力が育っていきます。
例:順番を待つソーシャルストーリー
すべり台の前に人がいるときは、順番をまちます。
まっているあいだ、手をつないだり、しゃべったりしてもいいね。
自分のばんになったら、すべり台をすべります。
「まてたね」と先生がほめてくれます。
まてると、みんなが気持ちよくあそべます。
💡ポイント
- 「順番を待つ=いいこと」と感じられるように書く。
- 「できたら褒められる」「みんながうれしい」など社会的な報酬を添えると効果的。
- 学校や公園など、実際のシーン写真を使うとさらにリアルに伝わります。
運動会や遠足が雨天順延になる場面のストーリー例
予定の変更は、特に自閉症(ASD)の子どもにとって大きなストレスになることがあります。
「どうして中止なの?」「いつやるの?」と不安になるときも、ソーシャルストーリーで「見通し」を持たせておくと安心です。
例:雨の日の運動会ストーリー
明日の運動会は、雨が降ったらお休みです。
雨が降ったら、来週の火曜日にやります。
ちょっとがっかりするけど、また練習できるのはうれしいですね。
晴れた日に、みんなで元気にがんばりましょう。
💡ポイント
- 「残念」などの感情も正直に入れてOK。
- 「でも、次の楽しみがある」とポジティブな締め方にする。
- カレンダーやイラストで「変更後の日付」を見せると安心感が増します。
ソーシャルストーリーがうまくいかないときの対処法
「興味を示さない」「聞いてくれない」ときは?
ソーシャルストーリーが効果的とはいえ、「そもそも子どもが聞いてくれない」なんてことも珍しくありません。
その多くは「内容が自分ごととして感じられない」「ストーリーが長すぎる」ことが原因です。
なので、対処法として以下のポイントをおさえましょう。
💡対処法のポイント
- 子どもの関心に合わせる
→ 好きなキャラクターや自分の写真を入れると、ぐっと集中してくれます。 - 短く・具体的にする
→ 1ページに1文くらいが理想。5〜6行で完結する短いストーリーにしましょう。 - 読むタイミングを変える
→ トラブル直後ではなく、落ち着いているときに読む方が効果的です。
また、「読む」ことが苦手な子どもには、絵カード風にしたり、音声で聞かせたりする方法もおすすめです。
「どうせ聞かない」とあきらめず、子どもが楽に理解できる形に工夫してあげましょう。
失敗例に共通する3つのポイント
ソーシャルストーリーがうまくいかないケースを分析すると、次の3つがよく見られます。
✖ 否定的な表現が多い
→ 「〜してはいけません」「〜しないでね」ばかりだと、子どもは不安になります。
⇒「静かにできると気持ちいいね」など、肯定的な言葉に変えるとよい◎
✖ 子どもの理解レベルに合っていない
→ 難しい言葉や長文はNG。「見通しを持てる内容」にすることが大切。
✖ 一度きりで終わっている
→ ソーシャルストーリーは「読むたびに理解が深まる支援法」。
なので、定期的に読み返し、状況に応じて少しずつ内容を更新する。
上記が失敗しやすい・うまくいかないケースなので、注意してください。
これと逆を意識して取り組むと、ソーシャルストーリーはうまくいきます。
効果的に伝えるためのコツと親の関わり方
ソーシャルストーリーの効果を高めるには、「親や先生の伝え方」と「関わり方」がとても大切です。
💡効果を高める3つのコツ
- 安心できる雰囲気で読む
→ 叱った後ではなく、穏やかな時間に。「一緒に読もう」と誘うのが◎。 - できたことをすぐに褒める
→ 「ストーリーみたいにできたね!」と声をかけることで、行動が定着します。 - 一緒に作る・選ぶ
→ 子どもと一緒に登場人物や場面を選ぶと、自分ごととして受け止めやすくなります。
「できなかったところ」ではなく、「少しできたところ」に注目してほめましょう。
小さな成功体験を積み重ねることが、行動の定着につながります。
ソーシャルストーリーに関するよくある質問

Q.何歳からソーシャルストーリーは使えますか?
A.幼児期(3歳ごろ)から小学生まで、幅広い年齢で活用できます。
ただし、年齢よりも「理解力」に合わせることが大切です。
言葉の理解がまだ難しい子には、写真やイラスト、実物の写真を使うとより効果的です。
Q. どのくらいの頻度で使うのが効果的ですか?
A. 新しい場面に挑戦する前(例:遠足・病院・登校再開など)や、苦手な行動が出そうなときに事前に繰り返し読むのが理想です。
一度で理解できなくても、何度か読んでいるうちに安心して行動できるようになる子が多いです。
Q. 保護者が自分でソーシャルストーリーを作ってもいいの?
A. もちろん大丈夫です。むしろ家庭でのソーシャルストーリーは、子どもがよく知っている人・場所・場面を使えるため、より効果的です。
絵カードや写真を使いながら、「これからどうするか」「どう感じるか」を一緒に考えるようにすると、子どもも前向きに受け入れやすくなります。
まとめ|ソーシャルストーリーで、発達障害の子が安心できるサポートを

ソーシャルストーリーは、特別な支援が必要な子だけでなく、みんなに役立つ方法です。
「はじめてのことがこわい」「人と話すのが苦手」など、誰でも感じる困った気持ちをやさしく助けてくれます。
家庭でも、学校でも、療育でも、
まわりの大人がいっしょに使ってあげることで、子どもは少しずつ社会のルールや人との関わりを学び、自信を持って行動できるようになります。
ソーシャルストーリーは、子どもが安心して成長できるおまもりのようなもの。
ぜひ、あなたの目の前のお子さんにも、ピッタリのストーリーを作ってあげてくださいね。